外厩制度の概要と役割
外厩(トレーニングセンター)とは、競走馬がレース終了後に入厩する調整・リフレッシュ施設のことです。中央競馬(JRA)では厩舎(美浦・栗東)に入厩して調整を行い、一定期間休養・放牧後に再び厩舎に戻るのが一般的です。しかし、外厩制度とは、レース終了後に直接外厩へ移動して調整を受け、そのまま次のレースに向けて競馬場に行くことができる制度です。このように外厩で調整・リフレッシュしてから次のレースに出ることで、厩舎の負荷を軽減しつつ競馬の連続性を高める効果が期待されます。
現在のJRAには外厩制度が導入されておらず、全ての馬はレース後に厩舎へ戻ります。ただし、外厩は北海道競馬では導入されており、ホッカイドウ競馬では外厩を経由して直接競馬場へ出場できるのが特徴です。海外ではこのような外厩制が主流であり、日本でも一部の民間外厩が存在します。外厩は主に休養中の馬のリフレッシュや入厩前の調整、調教師が直接調整できる環境を提供する役割を担っています。実際、外厩では各馬を専用の馬房に入れ、飼い葉つけや調教を行い、レースに向けて仕上げていきます。レース前に厩舎へ戻すのは一般的に2週間前~1ヶ月ほどで、それまでは外厩で調整します。
JRAでは調教師が管理する馬房数(厩舎の数)は、厩舎の成績に応じて増減する「馬房のメリット制」が存在します。例えば超一流レベルの調教師であれば28頭分の馬房を使える場合もありますが、成績が悪ければ馬房数が減少します。一方、外厩は民間施設であるため、調教師による直接の管理は行われませんが、調教師との連携によって各馬のトレーニング計画を実行します。このように外厩は調教師の自前の厩舎に頼らずに調整できる場所として、競走馬の健康管理や調教効率の向上に貢献しています。
外厩制度の導入について、JRA側は「既得権益の守り」という観点から慎重な立場をとっていると指摘されています。厩舎が増えれば厩舎のメリットが減るため、外厩制度は既得権益を損なう恐れがあると見なされています。また、外厩が普及すると調教師は外厩で調整できるため、厩舎に戻らない分、厩舎作業への集中が難しくなる懸念もあります。一方で、外厩は厩舎が不足する場合の救済策としての意味合いもあり、厩舎がいっぱいになっている際には外厩で調整してから厩舎に入ることもできます。総じて、外厩制度は競走馬の調教・リフレッシュに新たな選択肢をもたらすものの、JRAの既存制度との調和や厩舎側の意見を踏まえつつ、将来的な導入検討が行われている状況です。
主要な外厩施設とその特徴
日本ではノーザンファームや社台ファームなどの大手ファームが自前の外厩施設を構えており、これらが競走馬の調整に活用されています。以下では、ノーザンファームと社台ファームに関連する主な外厩施設を中心に、その所在地、面積、収容能力、施設内容、主要な利用馬、および開業年などを比較します。
ノーザンファームしがらき(滋賀県)
- 所在地: 滋賀県甲賀市信楽町神山
- 敷地面積: 約28ヘクタール(東京ドーム6個分)
- 収容能力: 約370頭(12棟の厩舎、370馬房)
- 施設内容: 屋外800m直線坂路コース(高低差39.7m)、屋外900m周回コース、角馬場2面、屋根付きウォーキングマシンなど。坂路コースでは3台のカメラで馬を自動追跡し、調教師の技術向上にも活用されています。
- 主要な利用馬: ノーザンファーム(NF)関係の栗東所属馬が中心に利用されています。例えば、美浦所属の堀宣行厩舎の馬がノーザンファームしがらきを外厩として利用することが知られています。また、ノーザンファームしがらきはオルフェーヴルやジェンティルドンナなどの名馬を育成・調整した基地でもあり、その実績が高く評価されています。
- 開業年: 2010年秋に開場しました。開業当初にはグリーンウッド・トレーニングからノーザンファーム関係の馬とスタッフが移動し、さらにノーザンファーム各施設からスタッフが結集して開業しました。
ノーザンファームしがらきはノーザンファーム傘下の関西地区の前線基地として、栗東トレセンから車で約30分の立地にあります。この施設は坂路コースが長く厳しい調教が可能であり、広大な敷地によって馬がストレスなく過ごせる環境が整っています。実際、しがらきで育成・調整された馬は多くのG1勝利を収め、厩舎の信頼を高めています。ノーザンファームしがらきは「生産から育成、調教までを一貫して行う」方針を持ち、厩舎側との連携が密な外厩として機能しています。
ノーザンファーム天栄(福島県)
- 所在地: 福島県岩瀬郡天栄村小川字中曽根1
- 敷地面積: 約26ヘクタール
- 収容能力: 約355頭(12棟の厩舎、355馬房)
- 施設内容: 屋外900m坂路コース(高低差約36m)、屋外1200m周回コース、角馬場2面、屋根付きウォーキングマシーン・トレッドミルなど。
- 主要な利用馬: ノーザンファーム関係の美浦所属馬が中心に利用されています。例えば、イクイノックス(木村哲厩舎)やソングライン、スルーセブンシーズなどがここで調整を受けました。また、ノーザンファーム天栄はアーモンドアイやイクイノックスなど数多くの名馬を育成した施設でもあり、現役のデンクマールやブラックゴールドなどがここで調整中です。
- 開業年: 2012年1月に開場しました。
ノーザンファーム天栄はノーザンファーム傘下の関東地区の前線基地として、福島県天栄村に構えられています。美浦トレセンから約230km、車で3時間程度の立地です。施設には広大な敷地とともに厳しい坂路コースがあり、美浦の厩舎が不足した際にも活用されています。ノーザンファーム天栄は米本昌史調教師が初任地であった施設でもあり、現在は木実谷雄太場長が率いるスタッフによって、静かで自然豊かな環境の中で馬の育成・調整が行われています。ノーザンファーム天栄では「声かけを率先する」ことが強調されており、スタッフ同士の良い人間関係が名馬を育む土壌となっています。この施設はノーザンファームの生産から育成、調教まで一貫した方針に沿い、デビュー前の馬から現役のG1馬まで幅広い成長段階の馬を管理しています。
山元トレーニングセンター(宮城県)
- 所在地: 宮城県亘理郡山元町坂元字一ツ橋1番
- 敷地面積: 約43ヘクタール
- 収容能力: 約300頭(10棟の厩舎、約300頭収容可能)
- 施設内容: 屋外900m坂路コース(最大勾配9%、ウッドチップ、3F計時システム)、屋外1100m周回コース(ウッドチップ)、角馬場50×50m、屋根付きウォーキングマシン20基、トレッドミル7基、練習用ゲート2基、逍遥馬道800mなど。
- 主要な利用馬: 社台ファーム関係の馬が中心に利用されています。例えば、社台ファーム生産のダイワメジャーやネオユニヴァース、ヴィクトワールピサ、ソウルスターリング、オメガパフューム、レッドルゼル、ダンシングプリンス、スターズオンアース、アスクビクターモア、デルマソトガケ、ソールオリエンス、シャンパンカラー、ジャンタルマンタル、ダノンデサイルなどがここで育成・調整を受けました。
- 開業年: 1992年に開設されました。
山元トレーニングセンターは社台グループが1992年に東北地区に設置した外厩施設で、社台ファームの生産・育成拠点として重要な役割を果たしています。当初は社台ファームのデビュー前の馬の育成や休養中の馬の調整に用いられ、その後はノーザンファームや追分ファームなど他のクラブ馬も利用するようになりました。施設には全国屈指の設備が備わっており、最大勾配9%の坂路コース(長さ900m)は美浦・栗東の坂路(最大勾配4.5%程度)を上回る厳しさで、このため社台ファームの馬は坂路コースで鍛えられています。また周回コース、屋根付きウォーキングマシン20台やトレッドミル7台など、様々なトレーニングメニューが可能です。山元トレセンは2020年に坂路コースを900mに延長し、さらに施設改良を進めています。この施設は東日本大震災の際にも高台に位置し、津波被害はなく、また自家発電機により在厩馬への影響を最小限に抑えられたことで知られます。山元トレセンは社台ファームの屋台骨となる施設であり、ダイワメジャーやネオユニヴァースといった多数のG1馬を育成してきました。現在も上水司場長を中心にスタッフが乗り出し、社台ファームの次世代の名馬を育む中核拠点として機能しています。
その他の外厩施設
以上のほか、社台ファームやノーザンファーム以外にも、他の大手ファームや民間外厩が存在します。例えば、グリーンファームやチャンピオンヒルズなどは、それぞれ約3000頭以上の出走実績があり、一定の信頼性を持つ外厩として知られています。また、ノーザンファームが関東に設けたノーザンファーム空港牧場(千葉県)は、輸出検疫や海外遠征前の調整に使われる施設です。この施設は2016年に開設され、オーストラリアなど遠征先での検疫基準に対応できる唯一の国内民間施設です。さらに、関東の栗東トレセンに近いグリーンウッド・トレーニング(滋賀県)は2001年に開業した外厩で、ノーザンファームしがらきが開設される前はノーザンファームのスタッフが常駐して関西馬用の外厩として機能していました。この施設は設備的には新しいノーザンファームしがらきに比べるとやや劣るものの、栗東から近く、蓄積されたノウハウや信頼から、社台グループを含む多くの調教師が利用しています。
また、関西の栗東トレセン周辺には社台ファーム鈴鹿(三重県)が2024年に新規オープンしました。この施設は直線1100m、高低差38m、メイン勾配3.5%のウッドチップ坂路と1周800mの周回コースを備え、馬房にはミスト設備も完備されています。高速道路のインターチェンジにも近く、栗東への輸送時間が1時間以内という利便性があります。社台ファーム鈴鹿は最終的に200馬房まで増設予定ですが、開業当初は50馬房でスタートしています。現在、社台ファームの関西馬は山元トレセンとグリーンウッドトレーニング、そして新設の鈴鹿を併用しており、厩舎が不足した際のリリーフ拠点として機能しています。
以上のように、日本の外厩施設はノーザンファームと社台ファームを中心に、関東・関西・東北にそれぞれ前線基地が存在しています。各施設は自前の特徴を持ちながらも、広大な敷地や厳しい坂路コース、最新のトレーニング設備を備え、それぞれ多くの名馬を育成・調整してきました。
外厩制度の効果と課題
外厩制度の導入によって期待される効果は、競走馬の健康管理の向上と競馬の連続性の確保です。まず、レース後に直ちに外厩で調整を受けることで、厩舎への戻りが不要となり、馬は過度なストレスや移動の負荷を減らすことができます。調整施設は専門的に設計されており、馬の体調に応じた適切なトレーニングやリフレッシュが可能です。これにより、馬の疲労回復が促進され、次のレースに向けた競走力の維持・向上につながります。例えば、ノーザンファームしがらきで育成・調整されたオルフェーヴルは2011年にクラシック三冠を達成し、ジェンティルドンナは同年に牝馬三冠を制しました。これらの名馬が外厩で調整されたことで、連続して高いパフォーマンスを発揮できたと言えます。
また、外厩は厩舎の負荷軽減にも寄与します。JRAの厩舎はメリット制により成績に応じて馬房数が決まっており、調教師は馬房が不足すると次のレースに向けての調整が難しくなります。外厩を活用すれば、厩舎に入れない馬も外厩で調整してから再び厩舎に入ることができるため、厩舎の過負荷を避けることができます。これにより、厩舎作業の効率化やスタッフの負担軽減も期待できます。さらに、外厩は競馬の連続性を高める効果もあります。従来はレース後に1ヶ月以上の休養を経て厩舎に戻ってから再調教を始めるため、連続して競争を続けることが難しかったです。外厩ではレース終了後に直ちに調整を受けるため、短期間で再びレースに出場することも可能です。これにより、競馬の頻度を上げたい場合や、グランドスラムを狙う場合など、競争のペースを速めることができます。
一方で、外厩制度にはいくつかの課題も指摘されています。まず、管理の難しさです。外厩は民間施設であり、調教師は直接管理できません。そのため、各馬のトレーニング計画や健康状態を把握することが難しく、調教師との情報共有が鍵となります。また、外厩で調整している間は厩舎から見えないため、監督の透明性に関する懸念もあります。JRA側も外厩で調整した馬が厩舎に戻った際の監督を行う必要があり、厩舎での調整と同等の管理が必要となります。
さらに、厩舎と外厩の連携も課題です。外厩で調整された馬はレース前に厩舎に戻るため、その期間の調教内容を厩舎側に正確に伝える必要があります。情報伝達のミスや不足があると、厩舎での調整がうまくいかない可能性があります。実際、外厩で調整している間の健康状態や走行データなどを厩舎側が把握し、適切な再調教を行うことが求められます。加えて、外厩制度が普及すると厩舎作業の重要性が低下し、調教師が外厩での調整に時間を費やすようになる懸念もあります。このため、調教師は外厩での調整と厩舎での管理の両面を両立する必要があり、作業負荷が増す恐れがあります。
最後に、既得権益の問題です。JRAの厩舎はメリット制により成績に応じて馬房数が決まっており、外厩制度が導入されると厩舎の役割が薄れ、既得権益を損なう恐れがあります。厩舎が減ると厩舎のメリットが減少し、厩舎スタッフの収入や地位に影響を及ぼすため、厩舎側の反発も予想されます。実際、外厩制度を導入する際には、厩舎側の意見を踏まえつつ、既得権益を極力守る対策が講じられる必要があります。
総じて、外厩制度は競走馬の調教・リフレッシュに新たな可能性をもたらす一方で、管理面や既得権益面で課題が残ります。現在のところJRAでは外厩制度は導入されていませんが、民間外厩の存在とその成果を踏まえ、将来的な検討が進められています。もし外厩制度が導入される場合、厩舎と外厩の協調体制や監督制度の整備、調教師の役割再定義などが重要な課題となります。それでもなお、外厩制度は競走馬の健康維持や競争力の向上に寄与する可能性が大きく、日本の競馬がさらなる発展を遂げる上での一つの選択肢となるでしょう。


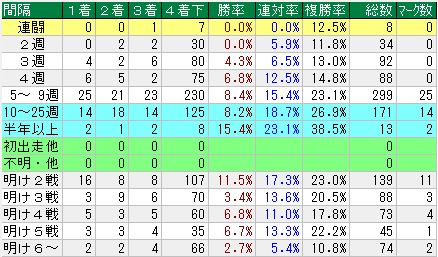
コメント